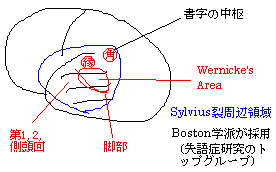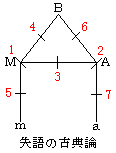言語の半球優位性とは、広く知られた概念である。しかし、我々の個体としての脳はきわめて複雑であり、解剖学的所構造も、言語の機能的諸構造の半球優位性ほどには半球差が大きくはなく、言語と脳との関係は、きわめて複雑な関係を持っている。
P.Broca以来、例えば言語においての半球優位性、すなわち脳の左右の言語機能の非対称性について、それを支持する様々な証拠が提出され、現在進行形で議論がなされている。GoodglassとKaplan(1983)は、「相互に明確に区別される様々な言語障害のパターンが、左半球のシルヴィウス構周辺領域のそれぞれ特定の部位の損傷によって繰り返し招じている」ことを観察しているが、それこそが、現在までに蓄積されてきた、言語機能の解剖学的局在についての知見である。
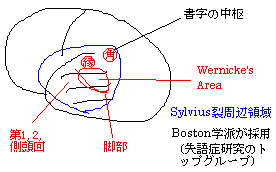
Broca失語(運動失語)
Broca領野、頭頂葉前下部、島、それらの深部白質が責任病巣。
非流暢性発話、反復・置換・省略・付加などの音の誤り、統語の誤り、書字の障害、喚語困難(失名辞)、失語の自覚が症状。言語理解は十分であるが、構音機能障害がある。左半球の前頭葉後部と頭頂葉前下部が、言語表出に関係する。
Wernicke失語
言語受容に関する障害。中側頭回から後後頭葉、縁上回下部と角回付近までが責任病巣。
流暢性発話、錯誤、新造語やジャーゴン、聴覚理解の障害、読みの障害、喚語困難、統語の誤り、病識の欠如がある。つまり、流暢に話すのだが、意味は通っていない。
伝導失語conduction aphasia
言語理解、発話の流暢性も比較的保たれるが、復唱のみが障害される。ほかに、音韻性錯誤、失文法、失名辞を伴う場合がある。古典モデルによれば、B-W領野を結ぶ、弓状束の損傷である。
前述したように、主要な言語皮質はシルヴィウス裂周辺領域である。失名辞は、病巣の局在が提唱されたことはなく、むしろ言語皮質の損傷につきものである。また、各モダリティを結合し、書字を成立させる中枢である角回の損傷によって起こる、失読失書alexia
with agraphiaは、それのみの症状が起こることはまずなく、聴覚理解や、失名辞も起こる。
超皮質性失語transcortical
aphasia
健全に残っている言語中枢と、他の高次認知機能と末梢との感覚、運動系から離断されている状態を、超皮質性失語という。言語中枢は健全であるため、復唱はできる。
言語領域の後部が他の部位と孤立すると、超皮質性感覚失語の状態になる。復唱ができる点が、Wernicke失語との最大の違いであり、流暢性発話、錯誤、失名辞のほか、反響言語がある。Goodglass&Kaplan(1988)は、「言語システムのなかの後部言語野が孤立すると、知識や意図、知覚などの関与する脳の他の部位と、孤立した言語機構との間の相互作用が成立しなくなる」
超皮質性運動失語は、皮質言語野の前部の離断によって、発話に関する運動プランに関する部位との連絡ができなくなる。補足運動野を含む領域、左前頭葉外側面が、責任病巣と考えられている。
発話開始の困難と、「とんちんかんな」会話反応がある。一酸化炭素中毒などにより、分水嶺領域が障害されると、言語野孤立症候群、あるいは混合型超皮質性失語とよばれる状態になる。自発話は喪失するが、言語野自体は生きているため、復唱と反響言語だけは認められる。
その他の離断症候群
・純粋語聾……聴覚には問題はないが、言語の聴覚理解が障害。左半球の一次聴覚皮質(ヘシュルの横回)の損傷と、右半球の聴覚連合野がウェルニッケ領野に連絡する線維も立たれている。
・純粋失読……左半球の視覚連合皮質の損傷と、右半球の視覚連合野から左半球の脳梁線維の切断。
・aphemie=verbal apraxia発語失行……理解は正常で、構音言語機能の障害。
・純粋失読……書字だけの障害。
古典的モデルへの反論
失語症研究が進むにつれ、その分析には、言語学的レベル(音韻論、形態論、統語論、意味論)をも含むようになり、それによって、失語症研究は古典論の境界を越えるようになった。例えば、各症候群に共通する音韻論的障害や、表出性の失語と受容性の失語に、似たような統語障害が出現することが明らかになってきた。また、読みの障害も、単一の過程としての「読み」ではなく、読みの過程に様々なレベルがあることやその障害、また読みとはそれらの過程の結合としてとらえられるようになった。
P.BrocaやC.Wernickeに始まる失語の古典論に対して、そのモデルが人間の言語を、単純に考えすぎていることが批判されるようになった。
言語と半球優位性の問題
古典的モデルでは、脳内で実現されている言語機能は単一の部位に対応しているという、局在論の立場をとる。その局在は、主に左半球であり、右半球はそれほど言語には関連しないと思われていた。しかし、これと反することが実験的に明らかになっている。
右半球の言語機能を見るためには、例えば、left
hemispherectomy左半球切除術の患者を研究する事によって、右半球の言語機能がどうなっているかが分かる。ある研究では、言語理解に関して、麻酔が覚めた時点でも、失語症検査で使われるような「目を開けて下さい」などができる。術後18ヶ月まで記載されているが、一貫して'good'であり、相対的左半球優位程度の違いであるとしている。
しかし言語表出に関しては、発話も書字も障害があり、Jacksonが指摘したようなコミュニケーションを取るための命題言語が出てこず、emotionalなものなら出てくることから、言語表出に関しては、絶対的左半球優位が考えられた。
Roger Sperryの分離脳の研究では、二つの比較的独立した高次機能があり、右半球でも、言語理解力は保たれているということが確かめられている。しかし、表出には右半球が関係しているわけではない。そして通常は、右半球にも言語理解の能力があるが、左半球が抑制しているとしている。
また、Norman Geschwindは、higherレベルの感覚の連合によって、言語理解が起るため、本来、両側性に言語理解が起るのは、妥当なことであり、言語理解の半球機能差は、相対的な差にすぎないと述べている。
ならば、どうして言語表出は左半球に絶対的なのかについては、発話筋の神経支配、つまり脳と筋は、基本的には交叉性一側性支配を受けているが、Sperryと同様に、正中線に近づくにしたがって、両側性二重支配を受けているからであるとしている。しかし、最も精密な運動である言語表出の筋にとって、両方からインパルスが届くのは望ましくない。それによって子供の頃から、左半球優位が成立すると、Geschwindは考えた。
右半球が、言語に関与しているという可能性は、その機能がどこにあるのか、という問題を喚起する。しかし、その局在に関しては、いまだ十分な証拠を得られてはいない。
脳内の言語機能局在
古典的モデルでは、脳内で実現されている言語機能は単一の部位に対応しているという、局在論の立場をとる。
失語の古典論が確立したのは、Wernicke&Lichtheimまで遡ることができるであろう。以下に、彼らのモデルを簡単に図示した。
Wernicke-Lichtheimの失語図式
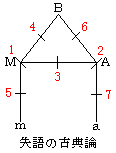
M:運動性言語中枢 A:感覚性言語中枢 m:発話の運動器官 a:聴覚器官
B:皮質の言語器(M,A)を刺激して活動させる皮質の広範な部位の図式的表示。特定の部位を指すのではない。概念中枢にあたるもの。
1.皮質性運動失語
5.皮質下性運動失語(純粋語唖) 表出性、運動性の失語
4.超皮質性運動失語
2.皮質性感覚失語
7.皮質下性感覚失語(皮質聾) 皮質性の失語
6.超皮質性感覚失語
3.伝導失語
これらは、それぞれの機能的中枢と、それらの連絡をする線維結合から、言語の神経機構を考えているが、それが必ずしも正しくないことが、現在の神経解剖学や生理学から徐々に明らかになっていった。
第一に、脳内のニューラルネットワークは、並列分散処理を行っているであろう。第二に、弓状束のような構造では、つまりB-Wを結ぶ線維では、情報が双方向に流れている。
つまり、脳内のある部位は、ある機能と一対一対応をしているわけではなく、多数の機能に関与している。このことは、古典的モデルとは一致しない。
また、古典的モデルでは考慮されていなかった、島、側頭葉後内側部、後頭葉内側部、前頭葉上内側部、頭頂葉前部の上内側部、頭頂葉上部、側頭葉外側下部などが、言語に直接関与していることが明らかになった。
さらに、古典論が想定している皮質領域のみならず、皮質下の領域(尾状核、被核、淡蒼球など)も言語活動に重要であるということが示唆されている。
皮質領域とそれらの線維連絡を想定する古典論のモデルは、部位的に明確に定義されているが、それだけを想定することは、もはや有益ではなくなってきている。
画像法
左半球の多くの領域が、言語過程に関与していることは疑いようのない事実であるが、言語の神経機構に関して、ニューラルネットワークモデルと、限定された機能局在を考えるモデルとの比較は、それほど単純な話ではない。
近年のニューロイメージング装置の技術的な発達により、非侵襲的な方法による研究が大きく進歩した。これは、健常者の様々な言語課題遂行中に生じる脳内の電気的活動を記録できるという利点があり、それにより、言語課題遂行中には、左半球のみならず、右半球の活動電位の変化が見られることから、右半球が言語に寄与している可能性の、物理的根拠を示した。
しかし、言語課題が、一次的に言語処理のみを反映していると信じる根拠はない。言語課題遂行中に活性化を示した右半球の領域が傷害されても、失語が起きないことを考えてみれば、PETやEGGは、言語過程そのものではなく、言語に生理的、運動的あるいは感覚的に関係した他の脳の過程を反映しているのかもしれない。また、活動電位の変化自体は、左半球よりも右半球の方が大きく、そのことも、これらの代謝活動の変化が、言語過程を一次的に反映している可能性を、弱めている。
どちらにしろ、技術的に高度なハードウェアを用いた研究が、言語処理の生理学的システム、特に脳内の機能局在に関しての理解をすすめるであろうことが期待される。
多くの神経学者が、言語過程について、皮質と皮質下を含む様々な領域の、並列分散処理過程を想定している。これに対する反証として、左半球の小さな局所的な損傷によって、極めて特異な言語障害が生じる例(例えば、左縁上回の小さな損傷によって、英単語の派生形態素の処理に障害が生じる例)がある。また、脳手術中に行われた脳の電気刺激データも、たった数ミリ刺激部位をずらしただけで反応が見られなくなるなど、並列分散処理システムに反するデータを提出している。
言語の神経機構についてのモデルの対立を解決するためには、生理学的なデータと解剖学的なデータを、よりよく説明しうる認知モデルが必要である。
|