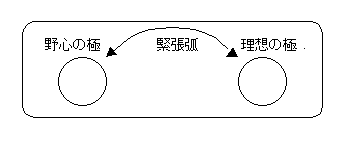
アーネスト・S・ウルフ『自己心理学入門−コフート理論の実践−』安村直己、角田豊訳、230頁、定価3780円、2001年。を参考にしています。
自己心理学の理論−ハインツ・コフートの理論−
【ハインツ・コフートの略歴】
1938年6月4日、フロイトはウィーンを離れ、翌5日2時45分にライン河をわたり、フランス領に入った。この時フロイトは「われわれは自由になった」と叫んだ。このウィーンを離れるフロイトを、駅で見送った一人の青年が、後年アメリカ精神分析学会会長となった、ハインツ・コフート(1913〜1981)である。
ハインツ・コフートは、1913年5月3日にウィーンで生まれた。ハインツの父はユダヤ人で、1936年、ハインツの大学生時代に亡くなったが、母のエルゼは渡米してアメリカ精神分析学会会長になった1960年代まで生きていた。ハインツの同僚の印象では、この母は〝ディフィカルト〟であり、ハインツ自身も冗談に〝クレイジー・マザー〟とよんだことがある。幼年時代のことを、ハインツはなんとなく悲しかったという思い出を語っている。
ハインツは一人っ子で、裕福な家庭に育ち、8歳から14歳まで大学生の家庭教師がついていた。19歳でフロイトが学んだウィーン大学医学部に進み、学生時代から精神分析に興味を持っていた。アウグスト・アインホルンから短期の精神分析を受けたが、フロイト自身とは会ったことがなかった。しかし前述のように、コフートはウィーンを去るフロイト一家を駅で見送っているが、これはハインツ自身の分身の欲求(後述)であるともいわれている。その数ヵ月後、フロイトの後を追うように英国にわたるが、パスポートもヴィザもなかったため移民キャンプに入り、1940年に正式のヴィザを得てアメリカへ渡った。
シカゴの病院でインターンを行い、その後シカゴ大学神経学科の住み込み医となった。1947年以降は精神医学に専念し、ルース・アイスラーに教育分析を受ける。その間シカゴ精神分析研究所に席を置き、1948年に卒業。ただちにそこのスタッフとなり、精神分析の教育と訓練を行い、シカゴ大学の精神医学の教授としても講義をしている。こうした精力的な活動の結果、1964年〜66年には全米精神分析協会の会長に就任し、古典的精神分析のスポークスマンとして「ミスター精神分析」と呼ばれるほど有能な分析家であった。
しかし、1971年の『自己の分析』をアンナ・フロイトはあまり評価せず、教育分析医のアイスラーの夫クルト・アイスラーは「コフートのやっていることはよくわからない」と述べている。こうした状況で、シカゴ精神分析研究所の委員会選挙で再選されず、国際精神分析学会の会長にも落選している。
そして晩年、コフートは、サンフランシスコの自己心理学研究会に病気中のところ出席した。彼は元気を出して「共感」についての講演を行った。講演の後、聴衆の拍手に「サンキュー」といい、別れ際にこうつぶやいた。
「今は休息をとりたい」 "I want to take a rest now."
その四日後の1981年10月8日、コフートは永い眠りに入った。
没後、彼の講演を元に『分析治療はどう行うか』(1984)が出版された。
【自己を体験すること――自己の構造と自己対象体験】
コフートは、始めは精神分析的構造モデルに付加的な考え方から出発し、新たに自己心理学として理論化する中で、特定の領域に貢献した。例えば、自己が傷ついて断片化していく発達上の出来事を組織化することに貢献した。
人間は環境から切り離された、心理的真空状態に存在できない。自己の出現と維持は、自己対象体験という、自己を喚起し、支え、反応する基盤の継続的な存在に依存している。すなわち、自己は、支持的な自己対象基盤に依拠し、自己支持的な反応の体験である自己対象体験を通して現れてくる。
自己対象体験には、映し返しmirroringと理想化idealizingの体験という2つのタイプがある。そこからコフートは、現れたばかりの自己は、二極性の双極構造を持っていると概念化した。自己の一方の極は鏡映自己対象体験の蓄積から構成されており、人から認められたい欲求の、野心の極である。自己のもう一方の極は理想化自己対象体験から生じており、理想と価値の極と呼ばれる。これらの極は、それぞれが異なる方向に自己を押したり引き寄せたりしているので、二つの極の間には基本的な技量や才能からなる緊張弧がかかっている。これが中核自己の核となる。自己の人生と調和して生きている人は、達成感を得ることができ、そうでない人は未達成感を伴った慢性の不満足感に苦しむことになる。
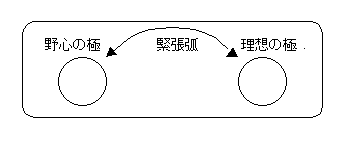
中核自己の構造
二つの極と才能と技量の緊張弧がおよそ等しい力で存在している時、それは調和してバランスの取れた自己といえる。しかし、自己の構成要素には、しばしば不均衡なウェイトがかかっている。理想の極の優勢さは救世主的人格の特徴を示しており、野心の極の優勢さはカリスマ的人々に見られる。組織人という盲従的な人格は、二つの極を犠牲にして、才能と技量の緊張弧が過度に優勢になっている。
そして自己を組織する自己対象体験の慢性的な剥奪は、豊かな応答性のある環境の中で育つ自己の構造的複雑さや力に満ちた活力が、相対的に欠如した状態にさせる。こうした人々の状態は、臨床的に興味が欠如した感覚や空虚感を伴った、軽い慢性的な抑うつ的ムードに苦しんでいる。
【自己対象体験】
自己対象とは機能であり、必ずしも人ではない。自己対象を自己の観点からとらえること、つまり自己対象を自己対象体験としてとらえることは、臨床的観察に合致している。自己の構造化をうながし、自分らしさを維持するよう働く全ての体験は、自己対象体験である。対象だけでなく、対象の代わりとなる象徴や概念の機能によっても、自己対象体験は生じうる。したがって、より厳密にいうと、自己対象とは自己でも対象でもなく、【関係性によって生じる機能の主観的側面】なのである。同様に、自己対象関係とは、精神内界の体験を指しているのであり、自己の支えにとって必要なイマーゴを指している。ただし、自己と対象の間の実際の対人相互関係を表現しているのではない。
親や養育者からの世話は、自己対象体験を子どもの中に喚起する。例えば、母親は子どもに話しかけたり世話したり応じたりする際、子どものための自己対象体験を作り出している。それは子どもの自己の組織化をうながし、自己が喚起され、維持される。この現れたばかりの自己は、ある程度の凝集性に達した時、自分であることの感覚として子どもに体験される。そこには、自己評価と幸福の体験が伴っている。
自己対象と機能の体験は人間が生きている限り必要なものであるが、この形態は発達していく。例えば、大人は子どものような身体接触や抱っこを必要とせず、小説や音楽、絵画や宗教から自己対象体験を得ることができる。
このように、自己対象体験の形態は、年齢に応じて適切な形が異なる。図式的にいうと、
(1)新生児は、現実の人との間で自己喚起的な体験を必要とする。その現実の人は、新生児に波長を会わせた反応を提供する。
(2)青年は、話し方や服装、音楽、アイドルのような若者文化によって提供される実在する人物やシンボルを通して自己支持的な体験をもつことが必要である。それらの対象やシンボルは、その有用性に応じて自己対象として機能する。
(3)大人は、芸術、文学、宗教、概念によって提供される実在の対象やシンボルを通して、自己支持的な体験を持つことが必要である。それらの対象やシンボルは、その有用性に応じて自己対象として機能する。
【自己対象欲求】
自己は、凝集性、活力、バランスを維持するために、自己を支える自己対象的な雰囲気が絶え間なく供給されていると体験されるような環境に囲まれて存在していることが必要である。この自己対象欲求は、いくつかのタイプに区別される。
1. 映し返しの欲求(Mirroring needs)
自己が承認され、確かなものとして認められて認識されたいという欲求。特に、自分自身を表現できたときに、それが受け入れられ、評価されたいという欲求。
2. 理想化の欲求(Idealizing needs)
自分自身を、賞賛し尊敬している自己対象の一部分として体験したいという欲求。安定し、落ち着いた、力強く、賢く、保護的な自己対象に受け入れられ、溶け込みたい欲求。
3. 分身への欲求(Alterego needs)
自分が自己対象と本質的に似ていることを体験したい欲求。
4. 対立への欲求(Adversarial needs)
自己対象を支持的・応答的であり続けながら、少なくとも部分的にこちらの自立性を認めながら穏やかな形で自己に対抗してくる一つの力として体験したいという欲求。自己対象からの自己支持的な応答性を失うことなく、その自己対象と対峙し、対立的に自己主張して立ち向かうconfrontationという自己対象体験への欲求。
5. 融合の欲求(Merger needs)
a.
自己の延長:鏡映自己対象と完全に一体となる体験においてのみ、自己を確認できるような、原始的な映し返しへの欲求。
b.
理想化された自己対象との融合:理想化自己対象と完全に一体となることを強く求める理想化への欲求。
6. 効力感の欲求(Efficacy needs)
自分が自己対象に対して強い効果を及ぼし、必要な自己対象体験を自ら引き起こすことができるということを体験したいという欲求。
映し返し、理想化、分身、効力感、対立を求める自己対象欲求は、どの年齢でも存在している。乳幼児には、太古的な自己対象欲求が年齢相応なものである。大人においては、年齢相応に修正された欲求が成熟した自己対象欲求である。相対的に遅れた自己対象欲求は、発達が乱れた証であり、何らかの病理性を示唆するかもしれない。しかし、この太古的なモードは一時的にストレスの強い期間や自己の障害が慢性的にある場合は、まだなくてはならないものである。
【自己対象欲求の発達】
◇ 太古的な乳幼児
・融合 Merger
自己と対象が分化していない新生児や乳児は、おそらく自己と世界が限りなく融合しているかのように体験していると思われる。自己と対象が分化し、少なくとも一時的に自分であるという感覚sense
of selfhoodや構造化された自己が現れた後に、自己は融合状態と非融合状態を緩やかな形で揺れ動くようになる。しかし年齢が上がってくると、そのような融合状態は退行や病理性の存在を示しているかもしれない。
・映し返し Mirroring
乳幼児は自己の構造化とそれに付随する自分があるという体験を喚起するため、鏡映体験が必要であり、自己対象からの映し返しを求める。そうした鏡映自己対象体験に対する必要性は、一生を通じて存続する。
・理想化 Idealing
鏡映自己対象体験を求めることと同様、自己の構造を喚起し、維持するために、自己は理想化できる自己対象の存在を求める。この両方のタイプの体験が、自己感を喚起し、支えるために一生を通じて必要とされる。
・分身または双子 Alter-ego or Twinship
自己が他の自己対象と本質的に似ていることを体験し、自己の穏やかな支えとなる自己対象の存在自体によって、自己感が強められることが求められる。この分身自己対象体験は、次のエディプス期において確実に生じるといえるが、おそらく乳幼児期にも存在している。
・対立と効力感 Adversarial and Efficacy
これらの欲求はまとまりのある自己が現れる生後2年の頃にはじめて生じてくると考えられる。そしてこれらも一生を通じて必要とされる。
◇ エディプス期
エディプス期でも、映し返し、理想化、対立、効力感、分身自己対象体験が必要とされる。それは、自己が適切な性同一性を獲得し、後の精神神経症につながるような自己構造の歪みをもたらさないためにも必要である。そのためには、
(1)男子の場合
母親は誘惑的になることなく、息子の自律性と男性性を承認する。すなわち息子の理想化への欲求を受け入れる。父親は攻撃することなく、息子の対立と分身への欲求を受け入れる。
(2)女子の場合
男子の場合と逆。
◇ 潜在期
一生を通じて常に必要とされる映し返しと理想化の体験に加えて、潜在期においては模倣するモデルとして自分と似ている体験をするモデルとして自己対象が必要とされる。これらの分身の体験は技量の発達において重要で、仲間や親をモデルに学んでいく道を開く。
◇ 思春期
思春期においては、自己対象体験の様々な様式が徐々に拡大していく。自己対象機能の提供者は初期の養育者から教師や友人、人物の象徴的な代理物などに移っていき、自己対象の様式はより広がりを持つようになり、非人格化していく。
◇ 青年期および若い成人期
思春期に始まった過程が青年期に老いてより全体的に深まっていく。認知的な発達は両親の欠点の認識につながり、初期の理想化された自己対象は急速に脱理想化していく。親のイマーゴの脱理想化によって、自己対象が空白となってしまっては自己は存在し得ないため、青年は仲間集団や青年期に特有の文化やアイドル、英雄などに自己対象を求める。理想化された自己対象として、親の変わりとなる仲間集団を持っていることが、心理的健康を維持する上では重要である。また、歴史上の英雄や宗教、思想といった理想化の対象となる文化的な自己対象の存在が、価値の再構成と一般文化への統合を可能にする。このように、理想化された親のイマーゴは、青年の文化において理想化されたイマーゴと置き換わる。
青年は、エリクソンがモラトリアムと命名したこの時期を、大きなアンビバレンツと共に体験する。時間、余暇、お金、楽しみを持てることは喜びであるが、現実の責任をとる機会がまったくないことは屈辱的なことでもある。多くの青年にとって、はっきりしない将来よりも、今何者かになりたいという要請は抑えきれないものであり、またそれは大きな苦悩にもつながっていく。
◇ 結婚生活の時期
夫婦は、様々な自己対象機能としてお互いを使いあう。親密さは、自己の自律性を失うことなくコントロールされた原初的な融合への退行を促す。自己の境界を拡張して、相手を自分の中に包含することは、相手の自己支持的な自己対象体験に、自己の体験のように関与することを可能にする。他方、期待され、必要とされていた自己対象体験をめぐって欲求不満や失望が生じると、それは自己の凝集性を脅かし、夫婦関係を破壊するような行動を招くことになるかもしれない。
◇ 親になる時期
親は、子どもに必要とされた際には、十分な柔軟性と流動性を持てるような、しっかりとした凝集性のある自己を持っていることが理想である。自己の境界の流動性は、子どもを自己に含めたり、子どもを自律的に分離させたりすることを可能にする。ウェイスマン&コーエン(1985)は、夫婦の両親同盟parenting
allianceとは、親としての体験と課題を発展させていくために必要な、自己と自己対象の関係である、と述べている。
◇ 中年期
中年とは、自己を評価する時期である。したがって、自己の再評価とそのゴールの建て直しを受け入れてくれる自己対象が必要である。その対象から大きく外れると未達成の体験に終わり、中年の危機と呼ばれる状態に陥るかもしれない。
◇ 老年期
老年は、コミュニティを理想化する欲求を持っていることが特徴である。そのコミュニティの理想にとっての大切なモデルや指導者として、自己が認められることが必要な時期である。
【自己が危険にさらされるとき――自己の断片化と症状】
自己の凝集性、活力、調和を達成する際の重大な失敗は、自己障害の状態を生み出すといえる。病因論的にいえば、自己障害とは自己対象関係障害であり、自己対象体験の不全による障害である。
自己が凝集している状態から、構造が喪失した状態へ退行している場合、その人はこれを自己評価の喪失、あるいは空虚感、抑うつ感、無価値感や不安感として体験する。この自己の構造上の変化は、断片化と呼ばれている。断片化は、一般には不快な症状につながるような退行のことをいっているが、時折死が確かに迫っているような恐ろしさとして体験されることがあり、それは明らかに不可逆的な自己の解体を警告している。
退行し、断片化していく自己の主観的な体験は、あまりにつらいものであるため、このプロセスを逆行するためにあらゆる試みがなされる。自己評価を押し上げようとする試みは、しばしば自己を刺激したりする形を取り、自己対象体験が供給されるように環境に働きかけたり操作したりする。その結果生じる行動は、時に敵対的で、反生産的な効果すら与えるほど衝撃が大きい。その人の自慢話を聞く、尊大な態度を取られるなどは、大概の人にとっては迷惑であるが、いらつかせる行為が仕事や配偶者の喪失につながるような誤解やもめごとは、自分自身をより強く、より全体として感じるために、他人を利用しようとする脆弱な自己を持った人の自己評価の浮き沈みに由来している。しかし、逆に社会的役割は自己対象の機能を果たすことができる。断片化した状態にある患者がある組織に参加することによって、しっかりとした凝集性のある自己の構造に達するのを観察することはまれではない。
そして、「行動化」は、自己喪失のつらい体験を避けるための症状や行動の一つである。狂乱めいた生活スタイルや薬物濫用、性的倒錯、非行、仕事中毒、向こう見ずな刺激を追い求めること、強迫的なギャンブラーやアルコール中毒などは、自己組織を維持し、断片化した状態に陥るのを避けようとする絶望的な手段である。耐え難い断片化の局面から自分自身の気をそらし、自己が死んだような無感覚を遠ざけるため、このような行動化が起こる。
【攻撃性の二つのタイプ】
◇ 競争的攻撃性
目標の達成を妨げる障害物に対する正常で健康な反応であり、建設的なエネルギーとしても働く。欲求不満を生み出した障害が克服されたとき、自然に消滅する。
◇ 自己愛憤怒
自己愛憤怒は、自己を脅かし損傷を与える自己対象に向けられたものである。自己愛憤怒は、不快な自己対象が存在しなくなっても消えることはない。痛みを伴う記憶は後々まで残り、憤怒の念が煮え立っていく。そして、数週間、数ヶ月、数年間くすぶり続け、ある時点において、憎悪の念があからさまな敵意や激怒、冷酷な破壊性となって爆発する。
【共感】
病因となる可能性を決定するのは、支持的か否かではなく、自己対象の反応の性質である。したがって、欲求不満を起こさせる対象への激しい対抗心や競争的攻撃性は、分析の外で現れようと転移の中で現れようと、病的なものではない。そのような行動に自己対象に対する自己愛憤怒が混じっていなければ、解釈の必要はほとんどない。むしろ技術として誇張された中立性や過剰に長い沈黙といった、精神分析の技術上の規範が頑なに、過度に守られた時、しばしば自己対象反応の剥奪として体験される。治療の中で剥奪の体験が反復され、病因的な過去の体験に結びつくと、自己は攻撃されていると感じ、自己愛憤怒をもって自己対象(治療者)に立ち向かってくるかもしれない。こうした断絶は、説明と解釈によって自己の修復の機会になるかもしれないし、混乱の程度が激しければ、治療者との絆が破壊され、治療の中断を招くかもしれない。
自己愛憤怒がもっともよく現れるのは、境界例の患者である。それはいつも治療過程への脅威となるが、治療が継続したとしても怒りを納めるという困難な課題が残される。そんな時必要なのは、解釈よりも理解されることである。怒りが徐々におさまり、消えていくまで、共感的理解のみが必要とされる時期が、長期にわたって継続されるかもしれない。
他人が自分の内的体験に気づいており、暖かい肯定的な感情を持って反応してくれていると認識することで、その人の自己感は強まる。共感されることで、相手は自分に関心を持ち、自分を認めてくれていると考えられる。そのような承認を、鏡映自己対象体験という。この傾聴ということにより、被分析者の自己の凝集性を高め、自己評価と幸福感を高める(共感の自己を支える機能)。
Th.が明確化のための質問をするだけで解釈をせず、注意深く傾聴している時、Clは自分自身をよりよく感じはじめる。初期に存在した緊張が消失した、「調和的な」自己対象関係の時期が訪れる。これは今まで、転移性治癒あるいは治療同盟の成立とされていたものである。自己心理学的には、治療者の共感的な同調が、ClにTh.を自己の構造の一部として体験する自己対象として利用することを可能にしたと概念化される。Clの自己はこのように強められ、幸福感を増しながら、Clは自分自身の自己をよりまとまったものとして体験するようになる。
そして共感は、相手の体験の中にどっぷり漬かってしまうことなく、判断が曇らされないように、情緒的距離を維持する。Clが体験していることを知るのに必要最小限なだけ、Clの感情に参入し、味わう。
自己対象体験の応答性の様式は、単純なものから複雑なものまであり、年齢に応じて変化するが、少なくとも常に必要とされ、誕生から死ぬまで必要なものである。