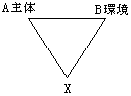
7月6日
前回までの議論
LPPは、ある実践共同体での適応として人間の学習をとらえていくため、2つの質的に異なる実践共同体への適応をとらえられない。
さまざまな実践共同体の間でうまくやっていくのは誰かとすると、認知主体としての個人への負荷が大きくなる(LPPの意義が薄れる)
↓
社会空間を複雑に記述していく方法論では、論理的に苦しくなる。その上、グローバルな経済・国際情報のなかで、比較的時間的・空間的に閉じた小さな集団の存立自体が難しく、人類学のほうも、人類全体の広いコンテクストの中で記述できなければならない。
↓
社会空間を複雑に記述していくこと一本では、無理。
Hodges Peripheralityへの疑問
実践共同体のあり方と自分との合致しない絶対的な距離marginality
→位相の異なる二つのシステムの交差点に学習概念が生じる。
→しかしこれでもまだ記憶を主体とした認知主体として、個人の負荷が大きくなる。
↓
他者との絶対的な距離
ミハイル・Bakhtin
コミュニケーションではなく、ダイアローグの概念
知識が一致していないことが本質的であって、コミュニケーションの概念のように、2者間の知識が一致して会話が終わることはありえない。両者の間に決定的なズレがあり、そのズレはなくならないがゆえに、対話の必然性があり、会話は終わることはない。
モノローグではなく、ポリフォニック(仮性的な言語空間)が構築される。
部屋のメタファー
同一時空間上に、2種類の物体が存在することはできない。たとえ、同じ部屋にいたとしても、原理的に見えているものがズレざるをえず、その差が埋まることはありえない。
=二者の間の絶対的な距離
↓ 相対性理論の多大な影響
この距離間は、他者の存在を前提としないと生まれてこない、その人だけの間。つまり、その人がその人でしかありえないようなその人らしいあり方というのは、他者の存在を前提としないと定義することも語ることも、そもそも生じてこない。
Hodgesは、社会的に定義される、その人しか占められない位置付けを問題にした。個々人の対面状況で生じる、どうしても一致できない側面を問題にし、その差異は、二者が存在することによって原理的に生じる。
LPPは、社会的構成が生まれると、ここのレベルを超えたレベルでしか定義できない社会システム性が生まれてくる点に注目し、システム相対的に個人を記述。
個のあり方が変わるという学習と、個人の間で生じるようなダイアローグ的な関係性が生じてくるような個のあり方(固有名性)が階層的に交叉しながら、二つのシステムが同時に展開していく。
フォトポエーシスのようなシステム論的にいえば、二つのシステムのあり方は相互に環境化していく(カップリングしていく)
↓
二つの独立した構成原理を持つシステムが、互いを環境化しながら展開していく中で、学習を捉えなければならない。
Y.Engstrom(フィンランド)の活動理論−拡張による学習−
※フィンランドは、心理学者の社会的ニーズが大きく、社会システムの改革などにも、エングストローム自身関わっている。
活動理論を社会文化に適用することに活動。
状況的認知アプローチで、エングストロームの活動理論とLPPが、最も現実的に使える。現実の複雑な社会システムをどう記述していくかの問題意識の中に、その中で学習し、変化していく人間という発想を取り込んでいるが、学習や発達とはそもそも何なのかということに関して、LaveやWengerとは異なる。
LPP……比較的固定的なものとしての実践共同体を想定。
活動理論……人が変化するとは、システムが変わることであると捉える。固定したシステムから何かを学び取って、自分が変化するのではなく、自分から積極的にシステムに働きかけることによって、個人も変わっていく。もともと精神発達の理論であった活動理論を、社会改革の理論として組み込んで、もう一度人間の学習などの概念を組み入れた。
活動理論active theory
・第一世代
ヴィゴツキー
記号に媒介された行為
↓
・第二世代
レオンチェフ
活動理論は、実質的にレオンチェフから始まっている。スターリニズム下で生き残るために、ヴィゴツキーの強調しなかった面を逆に強調した。
↓
・第三世代
エングストローム
活動理論から見たヴィゴツキー
媒介された行為(redimate action)……対象と直接に接するのではなく、間に媒介物が入っている。
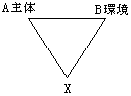
単に刺激があって反応があるという見方ではなく、人間の行為の構造は、直接対象に関わるだけでなく、様々な仲立ちを通して働きかけることが非常に多い
→それにより、多様な関わり方ができる。
どうして媒介物があるのか
社会的なコンテクストの中で編み出され、歴史的に蓄積されて次の世代に与えられている。よって、人間の行為は、基本的に社会的であり、歴史的である(単に、環境と直接向き合っているわけではない)。
→人間は、本質的に、社会的歴史的でしかあり得ない。
→もっとも重要な媒介物は、言語。
↓
ヴィゴツキーは、コミュニケーションを取るための言語と、思考を整理するための言語を分けて議論したが、スターリズムの中で、記号としての言語や暗示的な意味の言語を研究することができなくなった。
↓
記号的な言語という意味合いを弱める必要性
↓
レオンチェフは、活動の概念として、主体が対象に向かうプロセスに重点を置き、それに記号が付随しているとした。
レオンチェフの活動理論 著書『活動と意識と人格』
人間は、対象にある動機を持って向かうプロセスが行為の基本行動で、対象は、実社会的に歴史的に造られたものである。その対象に向かうことをサポートしているのが、媒介物である。
→活動のあり方・対象のあり方が、意識を決定する。
現実的な、物質的な基盤が、行為を決定し、行為が意識を決定する。
活動の構造の三つのレベル
活動を定義すると、主体がある動機を持って対象に向かっていくということ。
その動機は、個人が決定するのではなく、歴史的な状況の中で枠組みが決定されている。
活動の集団性……活動は、個人のレベルよりもむしろ、集団のレベルで決定されている(例:分業の概念)
Totalに何をやっているかというレベルと、その中で個人として何をやっているか(行為)。目的を達成するための下位の行為は、個人の側に多く存在していて、個人はその一部分を担う。
操作operation……目的や行為を達成するための技能。
↓
活動と行為と操作の各レベルは、様々にいったり来たりする。
レオンチェフは、この三レベルのダイナミズムをとらえることにより、人間をとらえようとした。その時に、様々なレベルで記号的なものが付け加わる(ヴィゴツキーは、行為が形成されるのは、記号的なものが介在するからこそであると考えた。その点が、両者の力点の違うところ)
次回:エングストロームの活動理論の展開