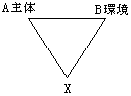
11月9日 接触論としてのヴィゴツキー
前回までの議論
・認知科学の想定する、学習転移論の問題点
学習とは、頭に知識を蓄えて、別の場面で使うことであって、ある文脈で学んだことを別の文脈でも使えなければならない。
→文脈が変わると、知識が使えなくなるのはなぜか。
→知識がうまく構造化されていないから(知識が不十分だったから)
→学習者がどのような知識を身につけたかに、移動の問題が還元される。
文化差や学習スタイルの違いなどの広いコンテクストが見えなくなる。
・参加論
学習する場の構造やシステムの中に、個人を位置づける
→個人ではなく、取り巻く社会的関係性の構造を見る。
→知識を取り込むのではなく、関係性の変化である。(EX.
LD児のアダム)
アダムのLDというのは、事後的に見えてくるものであって、事柄を1人で指示通りにやらなければならないということを前提とする教室内の見方と、料理クラブのような間の、言語共同体のミスマッチである。
脳に微細な障害がある結果ではなく、周りの人たちがどのように働きかけをするかによって、障害が見えたり見えなかったりする。
↓
実際の教育場面で認知科学を応用することは、できない状況の記述にはなっても、どうすればいいのか、どう関わればよいのか、あるいはその子の認知的欠陥と本当にいえるのかについて、まったく示唆がなくて使えない。
参加論では、関わりの構造から、結果としてできるできないが生み出されてくるから、例えば子供だけでなく、教師も理論的分析の範疇に入ってくる。
問題点
その場が個人のあり方を決めるということだから、社会的な方向に展開しすぎると、一人一人のこのあり方が逆にとらえられない。
→個的であると同時に社会的なあり方をしていることの関係のダイナミズムは、どうとらえるかという難しい問題をとらえなければならない。
→しかしLPPでは、社会的なあり方を記述することはうまくいったが、個的なものをあまりとらえられなかった。
↓
そして、Wengerは、人間は複数のコミュニティに参加していて、その組み合わせで個性が現れる(多重成員性)とし、その共同体でのメンバーシップの組み合わせ方(重点のおき方)は、個人が行っている(結節)。
→ところが、個的なものを成立させているのは、個人という話になってしまうため、個人主義に戻ってしまう困難が論理的にある。
参加論としてのヴィゴツキー
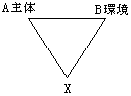
主体−道具、記号−対象の図式で、主体は直接環境と関わっているのではなく、媒介物を通して環境と関わることができる。また、道具は自分で自分に影響力を与えることができて自己コントロールができるところが、動物と人間の異なるところである。道具は、文化の中で歴史の中で作り出された、人間が作った人工物で会って、人間ははじめから、文化的であり社会的であり歴史的である。
参加論として読める、精神間−精神内図式
(例)記憶の使い方
子供と大人がオモチャを探す場面
→大人がその子の記憶を言葉によってコントロールし、検索の手順を大人が与える。
→はじめは、インターラクションの間で子供は検索しているが(精神間)、そのうち、その子自身が自分に語りかけることによって、一人でできるようになる(精神内へ)
↓
媒介物を、他者との関わりの中に参加していくことによって、自分のものにしていくことは、参加のプロセスの一つの見方としてできる。
→ヴィゴツキーを、参加論の先駆者として読める。
→媒介の概念を発展させなければならない。
Wertschの展開
本当に、ヴィゴツキーは参加論か
参加論としてヴィゴツキーを読んだ人の問題点は、どこにあるのか。
→Wertschらは、時間逆行的な視座で現時点からヴィゴツキーを読み直している。
参加論と一致しているヴィゴツキーの部分を引っ張ってくる。
↓
茂呂雄二……永遠の子どもとしてのヴィゴツキー
いまの研究から、それに近いものがあったとしてヴィゴツキーをみると、ヴィゴツキーは不完全なものとしてしか見えてこない。
↓
そもそも、ヴィゴツキーが何を言おうとしたかを(ヴィゴツキー自身の理論の射程や議論の展開がどうなっているのか)を内在的に読む必要があり、そうすることで、移動と学習の問題に新しい展開が出てくるのではないか。
「思考と言語」明治図書(絶版)
Мышление и речь 1934年
最新英語版 Thinking and Speech
・Thinking……世界を図と地のメリハリとしてとらえる。世界を区分して、構造化していって、自分の行為を作り上げる。
・Speech……音声をコントロールして文節化して発生する能力
→ヴィゴツキーは、考えることと話すことが結びついたところから生まれてくるものだから、意味と結びついた発話のことを指している。
世界を分ける能力と、音を出す活動が発達のある時点で組み合わさった時、意味が生まれてくる。それが人間にとっての現実的な意識である。
このような原理的なレベルから作られているという意味で、人間の意識や意味世界が作られているところから、人間は文化的であり社会的であるという話につながる。
媒介の概念は、ThinkingとSpeechをどうやって出会わせるのかについて、人間は様々なテクノロジーを発展させてきたということ。
↓
この関係性をどうとらえればいいのか、どう変化していくのかということをとらえることが、我々の経験する意味を理解することになる。また、世界が意味を帯びて現れるということ自体が、人間的な意識があるということと同義であり、考えることと話すことの関係性を分析することにより、人間の意識の問題がとける。
「思考と言語」
序章
1章:方法論
ThinkingとSpeechの関係をどう考えたらよいのか
2章:ピアジェの自己中心的言語批判
最初の言葉の機能は、大人と子供の関係を作るという単一の機能しかなく、社会的な機能のみ。自分と他者を結びつける。
↓
ある時期に言葉は他人だけでなく、自分自身に向けられる。
ヴィゴツキーにとっての自己中心言語は、子供が自分自身の思考に自分の言葉を媒介させる一番最初の形態で、思考の最も初期の状態。自己中心的発話は、他者がいない状況や外国人だらけの状況でも減ることはなく、逆に増えるときは、何か課題を解こうとしてうまく解けないときであり、思考のためにしていることである。
3章:シュテルンの人格心理学批判
4章:思考と言葉の交差
世界を区分して構造化してとらえる精神の働き(Thinking)と、言葉を話す働き(Speech)の発達は、生まれてから互いに独立して発達しているが、ある時期で交差する。その時(自己中心的発話が現れたとき)が、自分の思考と自分の言葉を関係づけはじめるとき(4,5歳と想定)で、高次精神機能、言語によって媒介された思考、つまり意味が生まれて意識が生まれてくる。
5章:概念ネットワーク論
では発達のある時期に結び合って、その段階で複雑な関係性が生じて来て、高次な意識や意味が生まれてくるなら、それはどのように構造化されているのかの議論。
↓
ランダムに交差しているのではなく、ネットワークのようになっており、ある一種の構造性を持って交差している。
それまでの心理学では、言葉とそれを示す対象との結びつきで概念が生まれると考え、その一対一対応は変わらないと想定。ヴィゴツキーは、その結びつき自体は、発達にしたがって変化すると考えた(この当時、概念は発達するという概念がなかった)
6章:生活概念と科学的概念
ネットワークが高度に発達したときに、科学的論理的概念ができる(概念と概念の関係で定義すること。例えば、食べるとはどういうことか)
その他方で、生活概念のような、言葉にして整理して定義しなくても、現実の行為に結びついた形で理解されて成立している概念(例えば食べること)
生活概念を足場にしないと科学的概念は発生しないし、科学的概念が得られることによって生活概念がより充実するような、相補的関係。思考と言語は、ネットワーク化した複雑な結び方をし、さらに多くのネットワークが互いに関係しあうプロセス。
7章:意味の発話的構成論
ネットワークは実在物か。
後づけ的に整理するとネットワークのようにみえるが、実体としてあるのではなく、実際に起っているのはThinkingとSpeechだから、時間の流れの中で展開する意味を帯びた発話行為のプロセスの中で、構造性が実現される。
ヴィゴツキーのやろうとしたこと――意識の解明
独特の複雑なシステムが、生物としての身体から発生してくる仕組みの関係の解明をしなければならない(バイオロジカルなシステムからサイコロジカルがいかにして発生してくるかの因果的に了解可能な形で説明することが、意識の科学である。
←もともと意識があるとするのであれば、科学ではない。
あると想定してから始めるのは、心の幾何学的な抽象的論理的世界が成立するだけで、現実的な意識をとらえるための方法ではない。
↓
意識の解明とは、発話と思考の関係の解明によってできる。その関係がどう現れるかのところに、社会的な部分が現れてくる。←参加論とは逆のアプローチ
心理機能としての思考と心理機能としての発話がであう(個々人の内部で起る)
↓
ネットワーク間の関係ができる。
↓
発話による他者に対する語りかけ
→個人から社会に開いていく独特のアプローチ(社会から個人をみていく参加論や、発達心理学とは逆の見方)
個を十分複雑に記述していくと、要素の連続線上に社会的なものにつながっていく。
方法論的な課題
考えることと話すことがどのように結びついていて、それが複雑になることによって、深く社会に結びついているかという話を展開しているが、それをどうとらえるのか。
次回:1章冒頭の、思考と言語をどのように概念していくかの解説